挨拶状の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

挨拶状の書き方と用途
挨拶状は、相手にお世話になったお礼の文書として差し出す場合もあれば、年賀状のように元気でやってますということを知らせるものとして送る場合もあります。相手の住所と名前または企業名、差出人の住所と名前または企業名などを正確に記載して、発送するようにしなければなりません。言葉は丁寧なものが原則ですが、親しい間の場合には、一文を添えてややくだけていても問題にはならないものです。
挨拶状の書き出し・結びの言葉
相手先の住所、所在地及び名城を記載します。なるべくならば株式会社等は略さない方が失礼にはならないものです。雛形が決まっている挨拶状もあるので、例文等を探して参考にしながら発送するように心がけます。通り一辺倒のもの以外で親しい人に送る場合でも手紙として差し出す場合には、口調は親しいものであっても口語体は避け、丁寧に記載することが大事です。
挨拶状の書き方の例文・文例01
挨拶状を誰に差し出すのかで変わってきます。目上の人や取引先等の場合には、日ごろお世話になっている旨を伝え、丁寧に記載をして行くのが常識です。年賀状等でも同様ですが、特に親しかったり相手が重要な人の場合には、一筆手書きを添えるのと感情がこもっていてよいとされています。送る側の工夫次第で単なる挨拶状も、受け取る側の心情は変わるものです。
挨拶状の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
相手が自分よりも立場が上か下なのかで多少変わります。ただ、受け取る側が不愉快な思いをしないで済むように、最低限のマナーの元で記載されなければなりません。書式などは特に決まっている定例的なものを除けば、特に横書きであろうと縦書きであろうと問題にはならないものですが、その文面と内容はよく吟味されたものでなければなりません。受け取る相手の心情をよく考えて発送することが大事です。
挨拶状の書き方の例文・文例02
年賀状や季節ごとで発送するものの場合には、定例的なものですから社会一般常識の元で記載すればいいとされています。ただし、その決まったものであってもちょっと一言付け足して手書きで近況などを添えると、受け取る相手にとっては通り一辺倒のものではないと分かり、心情的にも良い方向で受け取ってもらえることが多いため、考慮する余地は大いにあると言えるでしょう。
挨拶状の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
年賀状や季節ごとの手紙であればこちらの近況を知らせるものであるため、それほど格式ばった記載はしなくても問題はありません。一般常識の範囲で記載していれば十分ですから、そこまで凝りはなくてもよいとされています。受け取る相手の重要性と親しさで変更をすればよいものですから、あたり障りのないものを記載しておいても特に問題になるようなこともないと考えられるものです。
挨拶状の書き方の例文・文例03
定例的なもの以外の挨拶状の場合には、たとえば人生のビッグイベントとして開催されるもので、結婚式の案内状などを送る場合には、書式は決まっています。むしろその書式から外れたものを送るのは非礼に当たる可能性もあり、注意しなければなりません。こうしたイベントの案内状の類は世間一般で使用されている常識的なものを活用すれば、特に問題はないでしょう。
挨拶状の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
挨拶状自体が案内になっている場合です。この場合、そのイベント等への参加の是非の判断も行わなければならないものです。したがって、その文章も基本的には堅めのものとなります。言葉遣いも基本的には堅めにするように心がけ、失礼がないように丁寧に記載していきます。出席の是非を記載しなければならないようなものは、事前に電話で出席について確認をしておくのがマナーです。
挨拶状の書き方の例文・文例04
イベントでもそこまで形式ばったものではない、たとえば同窓会等の挨拶状などの場合には、やや砕けた表現でも問題がないとされます。しかしながら、相手が失礼に感じないように言葉遣いなどは注意して作成される必要はあります。その挨拶状を見て読んでみて、出席したくなくなるようなものは避ける方が無難です。一回そうした文書を送ってしまった場合には、次の出席も望めなくなることがあるからです。
挨拶状の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
人生の一大イベントでも特にないような時々開催されるイベントの類の場合には、やや砕けた表現で記載されていても受け取る側が不快に感じないレベルであれば、特に問題はないでしょう。ただし、文面が砕けすぎて受け取る側が失礼だと感じるようになると、出席が望めなくなります。したがって、あまりにも常識的でないようなものは避けるように、心がけておきます。
挨拶状の書き方の例文・文例05
人生の一大イベントでも死去等の悲報の場合には、特に注意して挨拶状を送らなければなりません。とは言っても今までの交誼に感謝するといった類の言葉を入れれば十分なケースもあれば、もう少し感謝の念を入れたほうがいいケースもあります。相手によってその書き方の工夫は必要ですが、厳重に何もかも縛られることはない程度のものです。事実を淡々と伝えることでもよい場合もあるでしょう。
挨拶状の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
親しい人に対して、その家族などが本人の死去などの事実を伝え、今までの交誼に感謝するといった内容の文書の場合です。死去の報告などの場合ですから、今後本人からの連絡があり得ないものです。つまり、挨拶状もこれが最後というケースもあるでしょう。そのことを念頭に置いて書いていかなければなりません。事実を丁寧に記載して、お礼を添えるのがマナーとなっています。
挨拶状の書き方で使った言葉の意味・使い方
挨拶状では誰に対して発送するものかという点と、それ以外でもその内容によっては、吟味して発送されなければならないものです。特に失礼があった場合などでは、招待する類の場合にはその招待に応じてくれなくなりますので、特に注意が必要です。言葉の使い方は常識的に使用するものを中心に考えていけばよく、あまり使用しないような言葉は避けることが一般的です。
挨拶状の書き方と注意点
受け取る側の立場に立って文章を記載していきます。このことを意識していないと、挨拶状がかえって相手の心証を悪くする可能性が出て来てしまいます。何のために挨拶状を送ったのか分からなくなりますから、出来るだけ丁寧に文書を作成し、相手が目上以外の人の場合でも、一定のルールは守って送るように心がけることが必要になります。言葉遣いも最低限のマナーは守ることが重要です。
挨拶状の書き方のポイント・まとめ
特に重要なことは、受け取る側の立場に立って行動していくということが大事です。文章も受け取って不愉快になるものは避けて、言葉遣いも礼儀をわきまえたものにしておくことが無難です。いくら親しかったものとはいえ、その後時間が空いていればそれだけ疎遠になっていることがあり、お互いの状況が変化していることもよくありますから、相手の立場に立って発送するように心がけておくことが求められます。
-

-
文章の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
文章を書く機会というものは意外と多いもので、手紙や論文を書くこともあれば、最近ではブログやSNSなどでも文章を書く機会が...
-

-
11月の手紙の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入...
11月は「霜月」とも言われていますが、その言葉通り、秋から冬に向けての月となります。11月の手紙としては、季節のお便りの...
-

-
案内文の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
案内文とは、言葉の通り「~~について案内する文書」のことです。案内文が必要なものは多数あり、なにかのイベントであったり、...
-

-
内部告発の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
内部告発はできれば誰もがしたくないことです。内部告発のリスクは必ずしも自分に返ってきますし、例え職場を辞めることはなくて...
-

-
qシートの書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
qシートとは演劇やテレビ番組、ラジオ番組において使用されるタイムテーブルを個別に記載しているもののことを言います。放送順...
-

-
ペット葬儀の香典袋の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味など...
ペットを飼っていない人またはペットを飼ったことのない人は、自分のかわいがっていたペットが死んでしまったときの悲しみがいか...
-

-
会議の議事録の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入...
企業などにおいて会議は重要事項の決定の場所となります。従って、何が話し合われたかを会議の議事録として残しておくことは必須...
-
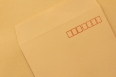
-
封筒の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
封筒には和封筒と角封筒があります。和封筒とは、ふつう用いられている縦長の封筒のことです。角封筒とは洋式の封筒のことです。...
-

-
原本証明の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
原本証明は何らかの書類についてその書類が間違いないものですということを、発行者が証明するために用いるものです。特に求めら...
-

-
考課表の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
考課表は主に企業等で働く従業員について、その人物の評価を行い昇進や降格、あるいは現状維持などの判断材料の一つにするために...
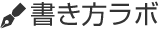





挨拶状は、相手にお世話になったお礼の文書として差し出す場合もあれば、年賀状のように元気でやってますということを知らせるものとして送る場合もあります。相手の住所と名前または企業名、差出人の住所と名前または企業名などを正確に記載して、発送するようにしなければなりません。言葉は…