香典の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

香典の書き方と用途
香典というのは仏式等の葬儀において死者の霊前等に供える金品のことを言います。用途の部分の書き方は神式の場合は「御霊前」「御霊前」と書きます。キリスト教式などでは十字架がプリントされているような香典袋が販売されています。白無地の封筒を利用する場合には御花料」の表書きをすることがあります。仏式の場合には、「御霊前」御香料」「御香典」と表書きします。
香典の書き出し・結びの言葉
書き出しの位置なども相手の名前は最も高い位置から書き出すように注意する必要があります。逆に差出人の名前は最も低い位置から書き出すようにしましょう。手紙が縦書きの場合は行の下の方に書き、横書きであれは右下の方に書きます。結びのあいさつには相手側の健康などを気遣うような言葉を使うことが多いです。便箋の最後の行はできるだけ1行ほどあまるように調整することがおすすめされています。
香典の書き方の例文・文例01
香典袋の書き方としては用途上水引きの上部分には用途を書き、下部分にはフルネームをバランスよく書くようにしてください。夫の代理で妻が会葬する場合には、フルネームの左下に「内」と書き添えます。夫婦揃って故人とのご縁があった場合には、連名で出すことがあります。結婚したばかりの場合でも新しい性で氏名をかくことが正式なマナーだとされています。
香典の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
不祝儀袋の場合は筆ペンなどを使ったり薄墨などで書いていきます。水引きの上部分に書く用途は宗教によって異なることがありますが、一般的に御霊前」が用いられることが多いです。下部分にはフルネームを書きます。夫婦連名や代理の場合は左下に「内」と記載します。結婚して間もない場合でも旧姓ではなく新しい性で氏名を書くことが正式なマナーとなります。
香典の書き方の例文・文例02
ビジネスなどで関わりがあったような場合には、会社名を書いて目上の方の名前を右から順番に書きますが、名刺を貼るケースもあります。3名くらいまでは右から左へと順に氏名を書いていくことができますが、4名以上になると書くスペースが少なくなりますので代表名の左に「外一同」と書きます。その他にも会社名を書いて部署名の下に「一同」と書くケースもあります。表袋はこうして連名にすることができますが中袋には全員の名前を書きましょう。
香典の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
ビジネスで香典袋を準備する場合には、会社名を書いて目上の方から順番に右から左へと名前を書いていきます。4名以上になってしまうようば場合は、表袋に連名で書くことができます。水引より下部に名刺を貼るケースもあります。特定の部署からの場合は、部署名「一同」とすることができます。表袋で連名にした場合でも、中袋には全員の名前を書くようにしてください。
香典の書き方の例文・文例03
香典袋の書き方として表袋の他にも中袋があります。中袋の表側には金額を漢数字で書くようにしてください。文字の向きによって書式が変わるため注意してください。裏側部分には名前の他にも住所を書いていきますがこの時省略してしまわずに郵便番号から書いていきます。表袋に住所を書いたから中袋には書く必要ないのではと思われがちですが、表袋と中袋は部別々に管理されることがありますので両方に住所を書くようにしましょう。
香典の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
香典には中袋が使用されていますが表側には金額を漢数字で書いていくようにしてください。5000円でしたら「金五阡円」と書き、お札は向きを揃えて新札は避けるようにしましょう。新札しかない場合は折り目を付けてから包みます。表袋にも住所を書きますが、中袋と別々に管理されることがありますので省略することなく郵便番号から住所を書いていくようにしてください。
香典の書き方の例文・文例04
やむを得ない事情にて弔問できないという方もいらっしゃいますが、このような場合には直接香典をお渡しできないため現金書留専用の封筒に入れて送ります。この時にお悔やみ状を一緒に送るようにしましょう。お悔やみ状には葬儀に参列して焼香することができないことに対してのお詫びの言葉を伝えることがよいです。「死ぬ」「死亡」などの言葉は使わずに「ご悲報」「お亡くなりになる」「ご逝去」などに言い換えます。
香典の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
やむを得ない事情にて弔問できない場合は、お悔やみ状と一緒に現金書留専用の封筒に入れて送ります。お悔やみ状を各場合には、時候のあいさつなどは省くようにして、すぐに本題に入るようにしましょう。葬儀に参列できないこと、焼香することができないことへのお詫びの言葉を書くとよいでしょう。死ぬや死亡などのような直接的な言葉を使わずに、「ご悲報」「ご逝去」などにしましょう。
香典の書き方の例文・文例05
家族を亡くされた場合のお悔やみ状の例文や雛形として「一日も早く悲しみを乗り越え、心穏やかに暮らすことができますようお祈り申し上げております」「一日も早くお心の痛みが癒えますよう、心よりお祈りいたしております」「やり場のない悲しみにくれております」「お力落としのことと存じますが、くれぐれもご自愛ください」などが用いられます。時々、重ね重ね、四苦八苦などのような重ね言葉を使わないように注意しましょう。
香典の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
お悔やみ状では、忌み言葉、重ね言葉などは避けて一日も早く悲しみを乗り越え、心穏やかに暮らすことができますようお祈り申し上げております」「一日も早くお心の痛みが癒えますよう、心よりお祈りいたしております」など遺族の心情を思いやる言葉を使います。重ね言葉や相手が不快になるような言葉を使わないように注意する必要があります。香典を一緒に送る場合は「心ばかりのものを同封しました」と書き添えるとよいでしょう。
香典の書き方で使った言葉の意味・使い方
香典には筆ペンを使ってもマナー違反になることはありませんが薄墨で書くケースもあります。薄墨には悲しみの涙で墨が薄くなってしまったという意味や、あまりの悲しみで力が入らずという意味があります。一般的に手紙を書く場合には頭語と結語を使用しますが、お悔やみ状では頭語や時候の挨拶などはすべて省きます。「合掌」で締めくくることは可能だとされています。
香典の書き方と注意点
薄墨で書く理由は悲しみの涙で墨が薄くなってしまったという意味を込めているからです。濃い筆ペンを使ってもマナー違反になるという心配はありません。お悔やみ状を書く場合には、一般的に手紙で使われる頭語と結語のセットを使用しないことです。時候の挨拶なども省いてすぐに本題に入ることがマナーとなります。ただしご冥福を祈って「合唱」で締めくくることはできます。
香典の書き方のポイント・まとめ
香典は表袋の水引きの上には用途を書き、下部分にはフルネームを書きます。会社で準備する場合には会社名と右から順番に目上の方から書きます。4名以上の場合は一同で連名にします。夫婦で連名にしたり代理で「内」と書くこともあります。中袋の金額は漢数字で書き、表袋同様に裏側には住所を書きます。やむを得ない事情で参列できない場合に悔やみ状と一緒に送りますが、お悔やみ状では重ね言葉や時候の挨拶頭語と結語は省きましょう。
-

-
香典の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
香典というのは仏式等の葬儀において死者の霊前等に供える金品のことを言います。用途の部分の書き方は神式の場合は「御霊前」「...
-

-
中学生の読書感想文の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味など...
読書感想文は小学校時代から夏休みの宿題として出される可能性が多いというのが現状でしょう。小学校ではなく、中学生の読書感想...
-

-
助けてもらったお礼手紙の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味...
世の中には親切な人がいるもので、困った人を見かけたら放っておけない人がいます。「もうだめだ、おしまいだ。」とあきらめかけ...
-

-
社外への報告書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記...
ビジネスでは様々な場面で社外への報告書を書かなければならない時があります。例えば商品の生産を一括管理する商社的な役割をす...
-

-
9人制バレーボール記録の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味...
近年、バレーボールの公式な大会はほとんどがコート内に選手が6人入る「6人制」で行われていますが、日本では9人制バレーボー...
-

-
会計報告書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
会計報告書は、たとえば職場内での従業員から飲み会などに充てる積立金や、あるいは町内会等での決算として最終的にその会計年度...
-

-
給与支払報告書摘要欄の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味な...
経理関係者が年明けに行わなければいけない書類のひとつである給与支払報告書ですが、給与支払報告書摘というのは、1月1日時点...
-

-
看護研究同意書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記...
看護研究同意書をきちんと書かないと倫理的に配慮が欠けた行動になってしまいます。看護研究を行う上で倫理的な配慮の項目が細か...
-

-
学校へ要望の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
学校へ要望を出す場合は、できるだけ人数を集めて提出することが大事です。一人の場合だとよほどの理由がない限り却下されてしま...
-

-
住宅営業での契約のお礼の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味...
住宅メーカーの営業マンにとって、営業住宅の契約の成立というのは、どんなに経験豊かな営業マンであっても嬉しいものです。その...
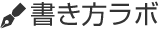





香典というのは仏式等の葬儀において死者の霊前等に供える金品のことを言います。用途の部分の書き方は神式の場合は「御霊前」「御霊前」と書きます。キリスト教式などでは十字架がプリントされているような香典袋が販売されています。白無地の封筒を利用する場合には御花料」の…