賞与評価シートの書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

賞与評価シートの書き方の用途
賞与評価シートは、いわゆるボーナスの査定に使用されるものです。査定を受ける本人がまずは記入し、それを上司が判定に用いるといった具合に処理が行われていきます。上司は直属の上司及び所属長などで評価され、その評価に基づいて次回の賞与の支給額に判定させる仕組みにするのが一般的です。この賞与評価シートはさらに、人事の昇進等にも使用するところも存在します。
賞与評価シートの書き出し・結びの言葉
賞与評価シートでは、まずは評価を受ける側が賞与の該当期間内において、目標の設定を行います。その目標の設定する意図と達成度合いなどを記載させ、それに対して上司などが一定の評価を与えていくという書き方がとられます。結びは、賞与をどの程度支給するべきかについての結論が記載されることになり、次回支給時の参考にすることなどが記入されて締めくくられます。
賞与評価シートの書き方の例文・文例01
賞与評価シートでは、その賞与をいくら支給するべきかの参考にするために記入をさせるものです。通常は本人がまずは客観的に自己評価を行い、その評価を受けて直属の上司がその評価と上司からの評価を行います。さらに、所属長などのより高位の人物が評価を行い、査定額としていくらが妥当なのかを記載して、締めくくることが一般的です。次回への本人へのアドバイスなどを記入する場合もあります。
賞与評価シートの書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
賞与評価シートでは、直近の賞与つまりボーナスの支給をいくらするべきかを考えていきます。そのための参考資料となるものです。まずは賞与を受ける本人からの自己評価を記入させ、次にその直属の上司が評価を行います。さらにその評価が妥当かどうかを考慮しつつ、所属長が賞与支給該当期間内における活躍の度合いなどを考えて記入し、評価を終えるのが一般的です。
賞与評価シートの書き方の例文・文例02
賞与支給の理由となる事案について、最初に絞り込む書き方です。つまり、特定の事柄について評価を記入し、そのことを持って賞与支給額の決定とするものですが、絶対評価を用いるのかあるいは他者との相対的評価を用いるのか、その時々で組織がしっかりと考えなければなりません。不公平感が出ないように工夫が求められ、開示をどこまでするのかも念頭に置いておきます。
賞与評価シートの書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
賞与支給の理由を、日常業務だけではなく特殊な事案が発生したときの事柄で評価を行う場合です。一定の期間内におけるすべての事柄についてではない場合で、絶対的評価なのか他者との相対的な評価なのかで記入の仕方も変えなければいけません。特に主観が入りやすい書き方は、後々公平性を問われます。開示をどこまでするのかについてもよく考えて執行する必要が生じます。
賞与評価シートの書き方の例文・文例03
元々賞与支給者や賞与を上乗せしたり、少し減らしたりする人員数を決められている場合が想定されます。このとき、事前にその評価を行って賞与支給額の枠が決められている以上、絶対的評価しか出来ず、しかも数が決められている以上、厳しい査定になりがちです。不平不満や士気に関わる可能性が高く、慎重に記載を行います。また評価を受けた側への説明責任も果たさなければいけません。
賞与評価シートの書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
賞与支給者や賞与の上乗せ、あるいは減額などの人員数を示されている場合です。このとき、限られた数しかその枠に入れられない以上、評価を行う側が厳しい査定を行わざるを得ない場合が想定されます。後々の業務において士気に関わる可能性が高くなるため、できる限り客観的にかつ評価を受けた者が納得できるような書き方をしなければなりませんし、説明責任も課されます。
賞与評価シートの書き方の例文・文例04
賞与評価シートでは書式がすでに人事当局によって決められていることが一般的です。その記載の仕方なども例文が示され、注意事項なども事細かく決められていたりします。そのルールの中で記入を行いますが、特記すべき事柄がその評価を受ける側にある場合は、賞与の増減についてしっかりと記入が成されなければならず、場合によっては評価を行う責任者が人事担当部局との調整が必要になるケースも出てくるでしょう。
賞与評価シートの書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
賞与評価シートの書式や雛形がすでに例示され、決められていることがほとんどです。ただし、その記載の中で特に特記すべき事柄がある人材の場合は、賞与の増減について一言述べてもよかったりあるいは述べるように指示を出されていることがあります。場合によってはその賞与評価シートの記入だけではなく、内容について評価を行う者と人事担当部局との間で、調整が必要になるでしょう。
賞与評価シートの書き方の例文・文例05
賞与評価シートの記入が出向中の人物に対して行わなければならない場合です。このとき、手紙等でやり取りを行う場合があり、その内容が第三者に漏れることがないように注意します。書き方は出向中の場合は出向先に依頼することもあれば出向元が一定の評価を行うこともありますが、いずれの場合も他者との評価に極端に理由なく差が出ることは、避けなければいけません。
賞与評価シートの書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
賞与を受ける人間が出向等で他の組織へと移っている場合です。このとき、評価を行うのが誰なのかを事前によく打ち合わせて決めておかなければなりません。さらに、出向先との間でやり取りをする以上は、こうした人事に関する内容が第三者に漏れることがないように十分な注意と配慮が求められます。なお、出向元にせよ出向先にせよ、評価が他者とかけ離れすぎることは避けなければいけません。
賞与評価シートの書き方で使った言葉の意味・使い方
賞与評価シートで使用する言葉は通常、である調で統一されるケースが多くなります。ただ、組織ごとで色々な取り決めを行うことも多く、そのルールの下で取り決めていけば問題がないものです。ですます調での記載はあまり一般的ではありませんが、評価を受ける本人が自己評価を行わなければならない場合には、ですます調での記載を求めることもあり得ることです。
賞与評価シートの書き方の注意点
賞与の支給に関する事柄である以上は、支給を受ける側にとってある程度は納得できるものにしなければなりません。したがって、客観的なものが求められることと、その根拠となる評価の仕方が必要になってきます。組織内での評価の仕方について、事前に説明なり評価の仕方記入例などがある場合も多く、それに沿いながら丁寧に記入を行っていかなければなりませんし、納得のいく根拠が必要になってきます。
賞与評価シートの書き方のポイント・まとめ
賞与の支給における決定的な理由となり得るものです。したがって、本人の自己評価が必要な場合であろうとなかろうと、その評価を行う側には一定のルールの下で、説明責任が果たせるようにしっかりと記入を行っていかなければならないものです。特に開示を行うことがある場合には、なぜその賞与の支給となったのか理解できるように、記述をしっかりとしておくことが求められます。
-

-
代表取締役社長での香典の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味...
そもそも、香典とはどう言ったものでしょう?香典は、仏式の葬儀の際に、死者の霊前に供える金品といった意味合いがあります。古...
-

-
秋のお礼状の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
秋のお礼状の書き方の雛形としては、秋にちなんだ時候の挨拶を入れた書式で、秋ならではの奥ゆかしさを踏まえながら書いていくこ...
-

-
大学教員の応募の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記...
大学教員の応募について、その書き方は様々な事例によって違います。それに則った例文や雛形、書式などはある場合もありますが、...
-

-
離婚での示談書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記...
協議離婚をする場合、役所に離婚届を提出し受理されることによって法律上離婚の効果が生じますが、それ以外の事由、例えば、慰謝...
-

-
住宅ローン控除連帯債務の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味...
住宅ローン控除連帯債務とは、具体的にどのようなことをいうのでしょうか。まず、前提として住宅ローンの控除について、簡単に説...
-

-
昇任での上申書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記...
昇任に関する上申書では、この上申書に記載する人の今後が大きく変わるだけに、よく注意して記載を行わなければいけません。また...
-

-
一言日記の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
日記をつけることは人生において意味のあることだと言えます。後で読み返した際にその時々の自分の心境を振り返ることが出来、現...
-

-
アポイント手紙の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記...
アポイント手紙を失礼のないように書けることによって得意先にも好印象を与えることができます。そのためにもきちんと雛形や例文...
-

-
調査依頼書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
調査依頼書を書く場合は、個人が民間の探偵事務所に依頼するケースが殆どです。内容は多岐に亘りますが、探偵事務所に依頼する場...
-

-
お金の念書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
お金の念書を書くことによって書類上での書いたことを保管することができるため、踏み倒されることがないように証拠を取ることが...
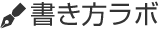





賞与評価シートは、いわゆるボーナスの査定に使用されるものです。査定を受ける本人がまずは記入し、それを上司が判定に用いるといった具合に処理が行われていきます。上司は直属の上司及び所属長などで評価され、その評価に…