衛生講習会感想の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

衛生講習会感想の書き方の用途
衛生講習会とは、職場において産業医や産業保健師、さらに衛生管理者や衛生推進者が参加して、職場で働く従業員の健康管理や危険な作業場所などを事前に話し合うことで、今後危険な状態にならないように注意をしていくための話し合いのことです。根拠法令は労働安全衛生法及び同規則で定められています。なお、産業医は出席できない場合もあるため、必ず出席しなければいけないわけではありません。
衛生講習会感想の書き出し・結びの言葉
衛生講習会に参加する人は決められています。また、管理者側になる人が感想を書くことはまずありません。衛生管理者や衛生推進者側に出席してみて、どう感じたのかを記載させるのが主たるものです。書き出し自体はどのようなものでも構いませんが、参加してみて今後どのように活かすのかは重要なポイントとなり得ます。結びは研修会として、今後望むことを記載するのが一般的です。
衛生講習会感想の書き方の例文・文例01
衛生講習会感想と表題を決め、まずは参加した人たちの雰囲気や所属する職場で活かせることがないかどうかを考えてみることでしょう。言葉などは通常使用しているもので構いません。その衛生講習会感想が参加していない人たちの目に触れることがあるためです。なお、職務等により出席が出来なかった人へは、まとめたものを手紙等で送付することが極めて大切で、置いてけぼりにならないように配慮が求められます。
衛生講習会感想の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
衛生講習会感想では、表題を決めてまた回覧するべき人によっては、衛生管理関係の専門的な用語はなるべく避けるなどの配慮が必須です。衛生講習会参加をしていない人にも常日頃から注意して欲しいことなどを知らせるという側面があるため、出来るだけ要点を整理するなどの工夫も求められます。参加が出来なかった担当者にも、資料を渡すなどの配慮が求められるところです。
衛生講習会感想の書き方の例文・文例02
衛生講習会で記載した方がよい内容としては、まずは現在の衛生管理の現況です。また、同じ仕事をする業界などでの問題点などがあれば、そのポイントを中心にして話をするなどの対応もあり得るでしょう。主催者側つまり通常は衛生管理を所管する部門が何を主眼に置いて話をするのかによりますが、法令改正等の現在の状況を把握し対応することは、極めて重要です。
衛生講習会感想の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
衛生講習会では、冒頭などによく現在の法令改正等の話がなされます。そもそも根拠法令となる労働安全衛生法や同規則における改正などは、衛生管理者や衛生推進者といった有資格者は必ず知っておかなければならないことです。また、その法改正が自らの職場にどのような影響が及ぼされるのかなども、担当者から話がなされますから、それに対する感想を書くことも大切となってきます。
衛生講習会感想の書き方の例文・文例03
産業医が出席している場合です。通常、産業医は掛け持ちで仕事をしている場合が多く、その事業所で専属で働いている場合を除けば、こうした衛生講習会に参加することはまれです。もし、産業医が出席をしている場合には、その産業医からは非常に重要な話がなされる場合があり、その要点を感想に記載することも必要になるでしょう。その話を受けて今後どうしていくべきかを考えることも求められます。
衛生講習会感想の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
産業医が衛生講習会に出席している場合には、産業医の講演や産業医が会議を引っ張っていく傾向が強くなります。特に職場に専属の産業医が配置されている場合には、必ずと言っていいほど出席をする熱心な医師もいます。したがって、その産業医を中心にした話になりがちとなりますが、主催者側によってその時々で様々な視点で話がなされますから、今後について話を聞いた結果どうしていくべきかを考えて、記載することも大切です。
衛生講習会感想の書き方の例文・文例04
グループワークのような形で衛生講習会を行う場合があり得ます。出席者同士で問題になっている事柄を話し合わせて、発表していく形式です。この場合、事前に問題点を考えておくように指示が出されています。突然考えろと言われても対応が出来ず、時間が無駄に使われることが多いためです。グループディスカッションが行われその主たる内容を記載し、それを受けてどう感じたのかを記載すれば問題はありません。
衛生講習会感想の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
グループワークのような形で、参加者に考えさせる場合です。このとき、出席者同士で問題点を話し合わせるため、事前に今の職場における問題点を考えさせたり、あるいは議題を与えてその件における問題点を整理して発表させることがあり得ます。衛生講習会の感想としては、自分の意見も述べつつ他の参加者の発言を受けて参考になった事柄を記載すればいいでしょう。
衛生講習会感想の書き方の例文・文例05
衛生講習会には様々なスタイルが存在します。毎回同じような内容だと参加者に飽きられてしまいます。したがって、参加を求める側は工夫を行うのが常です。その工夫の中で衛生講習会に参加してよかったこと、考えさせられたことを記載します。なお、重要なことは参加してみて今後どのように活かしていくかです。その主点をよく考えて記載を行えばよいでしょう。
衛生講習会感想の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
衛生講習会は主催者側がどう考えるかにもよりますが、様々なスタイルで行われます。毎回たとえば座学ばかりでは飽きられてしまいますので、グループワークにするのもその一つということです。工夫して実施した衛生講習会で得られたことなどを感想として記載してもらうことが大切ですし、今後職場においてどう活かしていくかも考えて、記載を行っていくことが重要となります。
衛生講習会感想の書き方で使った言葉の意味・使い方
衛生講習会では特に産業に関する医療や福祉の他に、健康管理の観点からの話が行われる場合が多いです。そのため、出来るだけ平易な言葉を使用して分かりやすくし、衛生講習会に参加していない他の職員に対して回覧がしっかりとなされるように段取りを行わなければいけません。担当者だけではなく、その担当者が持ち帰った知識を職場全体で共有できるように、感想の書き方も工夫することが大事です。
衛生講習会感想の書き方の注意点
後々職場に戻ってから回覧等を行うことが多いものです。したがって、分かりにくい表現や誤字脱字は避けて、なるべく例文や雛形をうまく利用して記載を行っていきます。感想は通常主催者側がすでに書式を整えていますから、その書式に従って空欄を埋めていく形で記載を進めていきます。後日、その感想文を主催者や所属の人が読みますから、読めないような誤字脱字などは避けなければいけません。
衛生講習会感想の書き方のポイント・まとめ
衛生講習会では、現在における関係する法令改正の知識や現状などを説明されることが多いです。したがって、それらをしっかりと聞き漏らさず、後日にどう活かしていくのか認識をしっかりと持たなければいけません。感想を提出するように求められている場合は、主催者だけではなく職場の人間など様々な人が目を通すことをよく考えて記載を行うことが極めて重要です。
-

-
賞与評価シートの書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記...
賞与評価シートは、いわゆるボーナスの査定に使用されるものです。査定を受ける本人がまずは記入し、それを上司が判定に用いると...
-

-
アルバイトでの職務経歴書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意...
アルバイトでも専門的な仕事だったりある程度職歴を求めるようなアルバイトの場合は、アルバイトでの職務経歴書を提出する必要が...
-

-
医療費控除での交通費の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味な...
医療費控除を申請するときは、家族全員にかかった医療費を合わせて申請することができます。医療費控除の申請ができる人は、実際...
-

-
委任状の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
委任状とは、代理権を授与したことを証明する書面のことを言います。例えば、交通事故等で保険金を請求することを弁護士に頼む場...
-

-
所得税徴収高計算書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味など...
所得税徴収高計算書は源泉所得税の納付書とも呼ばれ、所得税の源泉徴収を行っている者によって作成され、税務署や金融機関に提出...
-

-
準確定納付書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入...
準確定納付書での納付は、期限が定められています。相続をスタートする日から4ヶ月以内となっており、その間に納税しなければな...
-

-
残暑見舞いの書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
残暑見舞いとは立秋を過ぎてから白露の前日までに出す季節の手紙です。暑中お見舞いをもらったけれど返事を出しそびれてしまった...
-

-
レジ過不足始末書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと...
レジ過不足始末書については、実際の現金がレジ記録上の額と合わない場合に提出するのが、一般的ですが、その内容は出来る限り具...
-

-
表彰盾の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
誰かの行いを称えるときには、表彰状や景品などが贈与されることが大変多いです。それは世界全国で共通のことです。表彰状は紙に...
-

-
患者手紙の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
入院している患者や退院、転院する人に手紙を書くことで元気かどうかを確認することができ、相手もうれしくなります。また、病院...
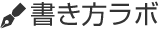





衛生講習会とは、職場において産業医や産業保健師、さらに衛生管理者や衛生推進者が参加して、職場で働く従業員の健康管理や危険な作業場所などを事前に話し合うことで、今後危険な状態にならないように注意をしていくための話し合いのことです。根拠法令は…