小論文の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
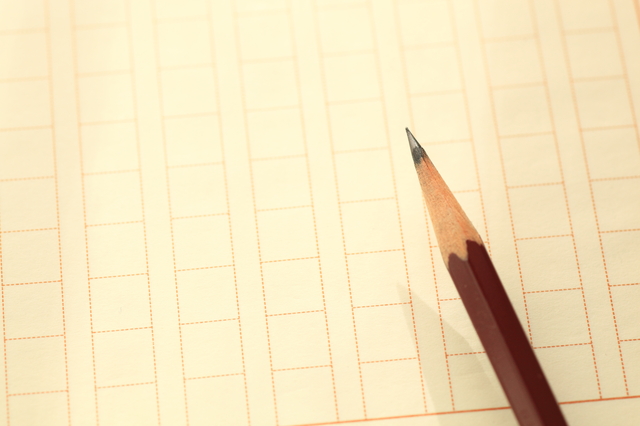
小論文の書き方と用途
小論文の書き方としては、表題の後に主題として結論を書きます。その後は起承転結に注意しながら、なぜこの問題や疑問点について考えようと思ったのか、あるいはこの問題点についてどう解決をしていくべきなのかを記載していく流れです。書式的にはこの流れで進みますが、途中疑問点なども交えながら、すべてがオール良しではない文面にしていくことで、メリハリがつきます。
小論文の書き出し・結びの言葉
表題として用いるものは、原則として指定されたものに限られます。また結びは結論として最初に用いたものと同じでなくてはなりません。最初の結論と最後の結論とが言葉が変わるのは構いませんが、結論が違うとすべての構想が壊れてしまいます。全体として何が言いたいのかが分かりにくくなりますので、最初と最後は同じ話になるように記載していく流れとなります。
小論文の書き方の例文・文例01
与えられた課題に対して、まずは表題を記載します。記載者の氏名などを記載するのは、文面の最後になるケースもありますし、最初に記載することもあります。その時々で変わります。また、起承転結になるように心がけて記載していきます。途中で他の手紙などを工夫して用いることは問題がありませんが、他の論文等の参考の場合も含めて出展などを明記しなければなりません。
小論文の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
手紙などと同じ内容で記載していくのは場合によりけりです。手紙を用いるのは原則として途中に用いるかどうかだけの話で、雛形はほとんど小論文の場合には決まっています。例文を参考にするケースもありますが、すべてを丸写しは論外ですし、厳禁とされているところです。言い回しなどにも注意してオリジナルの文面になるように十分に配慮しながら、記載をしていくことが求められます。
小論文の書き方の例文・文例02
他の論文などと同じような文面になるのは厳禁です。必ず作成者のオリジナルとして作成されるものでなくてはなりません。そのため、同じテーマで作成されているものと言い回しなどに注意しながら作成していきます。なお、起承転結については、その順番が論文の主眼から離れていなければ、多少文脈が前後することについては、問題がないとすることがあり得ます。
小論文の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
他者が作成したりあるいは過去に自分が同じような論文を作成しているような場合には、文面が同じようなものは厳禁です。あくまでオリジナルの小論文であることが求められます。したがって、似たようなテーマの小論文についてすでに記載がある場合には、十分に注意の上で対応を考えなければなりません。起承転結の順番が若干前後する点については、それほど問題にならないことが多いです。
小論文の書き方の例文・文例03
起承転結の流れで記載していくのが原則ですが、場合によってはこれが入れ替わるのも問題がないことがあります。ただし、この流れから逸脱するのは、作成している小論文の流れが支離滅裂になる危険性を秘めていますので、十分に考慮の上で作成を進めなければなりません。なお、起承転結の中で転の部分については、これが前後することはよくありますので、それほど気にしなくてもいいことがあります。
小論文の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
流れの変更は、その小論文自体が支離滅裂になるおそれがあるために、十分な注意が必要です。ただし、起承転結の中で転の位置が変わる場合についてはそれほど気にしなくてもいい場合があります。ケースバイケースということです。文面が矛盾しないように注意しながら作成を進めていきます。なお、結論はむやみに変更しないことが必須であり、求められますので注意が必要です。
小論文の書き方の例文・文例04
問題提起の方法としての小論文です。この場合は結論が出ない場合があり、または結論が出たとしても別の結論になることがあります。現在のところでは考えられる点が問題はないが、今後の研究如何によっては結論が変更される可能性があるということを示唆するような内容です。この場合はとりあえず現時点で判明していることについて、しっかりと記載していきます。
小論文の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
研究のテーマによっては、結論が今後変更になることがあります。そのことを念頭に置いて小論文を組み立てていくわけですが、今後の研究如何によっては結論が変わるおそれがあることを明記し、研究の進み具合によっては変更となることもあり得るという締めくくりになります。なお、変わる可能性があることについては、その可能性がどうしてあるのかを明記しなければなりません。
小論文の書き方の例文・文例05
別の論文と真っ向から対立するときには、こちら側の主張をしっかりと盛り込むことが大切です。また、他者との主張のの明確な違いを指摘し、どう違うのかをはっきりと主張していかなければなりませんから、他者の論文の主張でおかしな部分を明確にしていていくことが必要になります。その指摘が不十分だと、作成した側の意図が読み取れなくなりますから、主張が弱くなってしまいます。
小論文の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
他者がすでに論文にしている内容では、同じ内容のものではなく違う内容のものとなりますが、主張が真っ向から食い違うことがあり得ます。その場合どちらが正しいのかという話になりますので、相手の主張でおかしい部分を指摘していきます。その指摘の中で自分の主張とは異なり、その相手の主張がおかしいことを明記していきますが、その理由も記載が当然必要です。
小論文の書き方で使った言葉の意味・使い方
小論文の記載者が複数人いる場合には、代表者が誰でその論文について疑義がある場合などは誰に質問をすればいいのかなどを明記します。記載者が1人の場合には気にしなくてもいいことですが、複数人の場合には筆頭者があってその他に共同作業人として、小論文に記載します。連絡先電話番号の記載の他にメールアドレスなども明記するのが、最近の流れとなっています。
小論文の書き方と注意点
一人で小論文を作成した場合には一人だけ名前を書いて連絡先を書けばいいのですが、複数でその論文を書き上げた場合には、筆頭者が代表となり質疑などもその人が原則として受け付けるようになります。連絡先も代表者の元になるのが通例で、それ以外の人の連絡先などを記載するのはまれです。なお、電話番号以外の連絡先として、メールアドレスなども明記するのが最近では主流となっています。
小論文の書き方のポイント・まとめ
結論ありきで話をするのが小論文の書き方で、最後の締めくくりもその結論と同じになります。その流れの中で結論に至る経緯を起承転結を気にしながら書き進めていくことになります。ただし、起承転結が多少は前後しても問題がないこともありますので、内容によるものでしょう。なお、複数人がその論文を書いた場合には、責任者及び筆頭者が主な連絡先となりますので、その明記が必要になっていきます。
-

-
接待報告書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
多くの企業では、取引先に出張して接待を受けた場合、出張後に接待報告書を提出することを義務付けています。どういった接待を受...
-

-
フィールドワークレポートの書き方や例文・文例・書式や言葉の意...
フィールドワークレポートの書き方には、雛形や例文、書式などがそれなりに存在します。詳細はインターネットなどで調査して頂い...
-

-
バイト採用辞退メールの書き方や例文・文例・書式や言葉の意味な...
バイト採用辞退メールの書き方の用途は、まさにご自分がバイト採用を辞退したい時に参考にしていただきたいメールの書き方をまと...
-

-
狂犬病予防接種証明書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味な...
狂犬病予防接種証明書を書く際には難しく考えて書く人がいますが、要点を抑えて書くことによって簡単に書くことができます。狂犬...
-

-
葉書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
葉書は緊急連絡用としては、電話、ファックス、インターネットに全く太刀打ちできませんので、個人的な簡単な挨拶用、連絡用とし...
-

-
ねぎらい言葉の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入...
ねぎらい言葉を使用すると、どのような効果があるのでしょうか。仕事をする上で、家庭生活を営む上で、社会生活を円滑に送るうえ...
-

-
会社見学レポートの書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと...
会社見学レポートは実際に特定の会社にて業務内容を見学・体験し、そこで得られたものをまとめたものとなります。提出する理由は...
-

-
祝い袋お礼状の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入...
結婚や出産、あるいは子どもの節句や入学などに際して、お祝いをもらうことは多くあります。そんなときには、気心の知れた友達の...
-
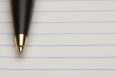
-
詫び状の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
詫び状の書き方ですが、通常の手紙と違うので、自分の近況などの記述は入りません。時候の挨拶なども必要ありません。まず、最初...
-

-
文章の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
文章を書く機会というものは意外と多いもので、手紙や論文を書くこともあれば、最近ではブログやSNSなどでも文章を書く機会が...
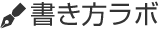





小論文の書き方としては、表題の後に主題として結論を書きます。その後は起承転結に注意しながら、なぜこの問題や疑問点について考えようと思ったのか、あるいはこの問題点についてどう解決をしていくべきなのかを記載していく流れです。書式的にはこの流れで進みますが、途中疑問点なども交えながら…